あっという間に、季節はすっかり冬の様相ですね。
周囲にも体調を崩す人が続出しております。これからの本格的な冬の到来に向けて寒さ対策、しっかり備えていきたい今日この頃です。
皆さまも健康第一で、2025年を乗り切りましょう!
さて改めまして…弊社、㈱Tenmaruは「組織づくりのお手伝い」をサポートしている会社でございます。
「採用」「育成」「組織変革」など、仕組みや育成で組織の一人一人が主体性を持ち、やりがい(ワクドキ)をもって自走できることをミッションに掲げています。なかでも「育成」は、コラムでももっとも多く取り上げているテーマです。
今ドキの若者の傾向を理解し、彼らに寄り添いともに成長する—
概ね、このようなことをお伝えしてきているかと思います。
しかし、最近、SNSやお客様との会話の中でしばしば話題となる「ゾス」文化。この「ゾス」には、私がコラムでお伝えしてきたこととは、一見、まるで真逆のようにも感じる意味が込められています。
「ゾス」はその時代に逆行するような内容と共に、しばしばセンセーショナルな受け止め方をされている一方、支持も批判も受けているような印象です。今回のテーマは、この「ゾス」文化について、私個人の感想を交えて、お話したいと思います。
「ゾス!」の衝撃
まずは「ゾス」が何かを知らない方に簡単に説明させていただきますと…
「ゾス」とは、「了解/承知しました/お疲れさまです」などの意味を持つ「オス」を、さらに強めた気合いの入った挨拶、という解釈で良いかと思います。
山本康二(通称ゾス山本)氏は、光通信で20代に取締役を務めたのち、グローバルパートナーズ株式会社代表となり、約1万人規模の組織構築、売上1兆円超とされる実績を築いた人物です。
彼の提唱する育成術を象徴するのが、「ゾス!」という挨拶というわけですね。
育成の特徴としては以下の通りです。
・高い期待をかける
「本人以上に期待してあげる」つまり、70や80という能力の人に対しても100や120を期待し、実際にそれを超えるように導いていく手法です。
・行動/実践を重視
「考えるより、とにかく行動する」「指示待ちじゃなく、自分の意思で道を切り拓け」と“量”と“挑戦”を後押しします。
・ハードな文化・言葉の掛け合いを通じた成長
挨拶「ゾス!」のように、気合を入れ、忖度や遠慮なくガツガツ根性で動けという雰囲気を作ります。「朝起きたら『ゾス』と言え。それだけで1日心が折れない」といった発言からわかる通り、理屈抜きの「根性と気合い、大声での挨拶」を重視しています。
・成果・スピード・数字重視
成果ベースの育成が根底にあり、結果がすべて、逆を返せば結果さえ出していれば、バックボーンなどは関係ないとされています。
・多様な人材受け入れ
それゆえに学歴・背景を問わず「やる気のある人」「強くなりたい人」にハードながら挑戦できる環境を与えています。結果、数字を出せる優秀な人財を得ることにも成功しているようです。
皆さまはいかがでしょうか?
私など、これを眺めているだけで、こんな前時代的なことをやって、それでしっかりと結果を出していること、本当にすごいことだな、と同時にハードな環境についていけるかな…と感じてしまいます。
「昭和はパワハラが横行してた」「前時代的なブラックな環境」など、私がこれまでコラムでお伝えしてきた内容は、恐らくこちらの「ゾス」的な育成方法とは正反対のスタイルではないでしょうか。
しかも、今の時代は「こんなことをしていると若者にはソッポを向かれてしまいますよ」ともお伝えしてまいりました。
ぱっと見は全方角から怒られそうな「ゾス」文化、当然といえば当然ですが、世間の受け止め方は賛否両論となっているようです。
「賛否」の「否」
こちらの会社での様子はテレビなど各マスメディアでも取り上げられておりますが、「パワハラ上等」といったセンセーショナルな報道は、なるほど確かに賛否の「否」を多く受ける結果にもなっているようです。
実際、若者の受け止め方も様々。
「ゾス飲み」と言われる、全員で歌い、踊り連帯感を深める飲み会は、個を大切にしたいZ世代からは
「あのノリについていけない」「強制的な雰囲気が怖い」といった声が多数上がっている現状もあるようです。

ハラスメントを起こしてはいけません、とさんざんコラムで書いてきた私にとってもこの方法は安易には取り入れることが難しい育成法だなと感じます。
※あくまでも個人的意見です。
「賛否」の「賛」
一方で、「ゾス」に対して好意的な意見も多くあります。
昭和世代の方が「昔はこれが普通。これくらいじゃないと成長できない」としたり顔で言っているのではなく、意外なことに、当事者である若手世代から多くの支持を得ているというのです。
実際、こちらの会社の若手社員からは、「厳しい環境に身を置いて成長してみたかった」「期待されていると感じる」「ビシビシ鍛えて欲しい」などの声が聞かれました。
実際に、「ゾス」式の育成は、離職率も低く大きな成長が期待できるということなのです。
寄り添い、一緒に成長しましょう。
厳しさを押し付けるのではなく、理解を示す。
ハラスメントは絶対に許してはいけません。
私が今までお伝えしていたことと真逆のことが起きている現実。なぜ彼らは「昭和的」育成法でしっかり成果を出しているのでしょうか。
「ゾス」が刺さる若者
ハラスメントやブラック企業などは、若手がもっとも避けたい就職先のはずです。
しかし、こちらの会社は最初から
「厳しい会社です」「パワハラ上等」と明確に宣言しています。
つまり、厳しい中でゴリゴリ成長したい!という意欲のある方しか、彼の会社の門を叩きません。
ブラック企業など、面接の際の説明とは違い、入社してみたらまったく条件が違っていた、ということが多いかと思います。
こちらの会社は、すべての情報をオープンにすることを信条としており、youtubeなどでも会社の様子を余すことなく発信しております。
これら一貫した情報開示により、厳しい環境を承知で自分自身を追い込みたい、と「納得」して入社しているため、入社後トラブルなどが起こりづらいのだなと感じます。
「優しい」育成に疑問を持つ若者
Z世代と言われる現代の若者ですが、人の本質は昔も今もそれほど変わらないかなとも感じます。
つまり、「世代別の傾向」はあれど、どの時代にも、いろいろな人がいるわけです。当たり前ですよね。
かつて悪しき時代と揶揄される昭和のモーレツ企業体質も、辛い、厳しいばかりではなく、あの環境で鍛えられて良かった、と思う人がいるからこそ、俗に世間が言う「ブラック体質企業」なども存在しているわけです。
もちろん理不尽なパワハラや法律無視のブラック勤務などは絶対にあってはいけません。しかし、「寄り添い」「理解」「共感」といった育成スタイルに、「生ぬるさ」を感じ、もっとビシビシ鍛えて欲しい!と感じるZ世代が存在していることも、実は当たり前のことなのかもしれません。
「多様性」は、現代的な価値観として若者に好まれる企業風土ですが、「厳しくして欲しい」という価値観もまた、多様性のひとつ。
確かな現代若手のひとつの姿なのですね。
根っこは同じ⁉
と、ここまで書いてきましたが、「寄り添い」的な育成と「ゾス」育成、真逆なように見えて、実は考え方には多くの共通点もあります。
いや、考えの根っこは同じ、と言ってもいいかもしれません。
こちらでお伝えしている通り、

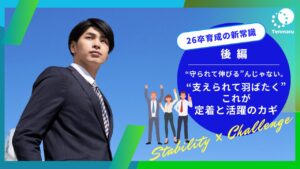
26卒世代は「安定」を求めつつ、そのうえでの「挑戦」への意欲を持っております。
一方、「ゾス」式では、
「信じる」「期待する」「行動させる」となるでしょうか。
つまり、根底にあるのは「若手を信用する覚悟」です。
若手を信じるというのは当然リスクを含みます。しかし、会社のその覚悟こそが、若手のモチベーションの源となっています。
会社を信じてください。あなたの挑戦を求めています。
整理して考えてみると、育成で大切な根っこの部分は似ているのではないかな、と感じるのです。
「寄り添い」の副作用
「心理的安全性」「寄り添う上司」「叱るのではなくガイドになる」
これらはすべて、私がこちらコラムで何度も取り上げてきたワードです。これらが育成において大切なのは言うまでもないことです。
しかし、時にこれらの文言が、間違った「副作用」を起こす危険性も感じるのです。
「若手の気持ちに寄り添うあまり、強く言えない」
「失敗されたくないので挑戦させられない」
こういったことが起こり得るのではないか、いや実はすでに起こっているのかもしれない。
寄り添うことは大切ですが、上司や先輩が若手社員の顔色をうかがって、伝えたいことが伝えられないようなことになってはいけない。心からの叱咤激励は、たとえ内容が厳しくても、真意が伝わっていれば、しっかりと若手社員にも響くはずです。
優しさと厳しさ
昨今「寄り添いましょう」式育成が、おおよそ浸透したところでリバイバルした「ゾス」育成。価値観が大きく変わる時、その揺り戻しがくるのも歴史です。

山本氏が「厳しい会社だ、ビシビシ鍛えて欲しいやつだけうちに来い!」と言えば、それに応える若手が集まり、しっかりと結果を出している。当人が成長できると実感できるのであれば問題ない話でもあります。
一方、そのような企業風土について行けないと思えば、自分に合った会社を探すでしょう。
やはり、相互理解と会社からの一貫した「開示」はとても大切なことなのだなと思います。
皆さまの会社での育成はどのようなスタイルでしょうか。
カラーは違っても、
若手は会社から信じられていると感じた時、挑戦し、大きく成長する。
ここだけは揺るがない育成の基本なのかもしれません。
今回は「ゾス」の衝撃的な育成法についての所感をお届けしました。
一概に「良い」「悪い」と断じることはできない、でも、その厳しさにも確かな真実があるな、というのが私の感想です。
そして「寄り添う」育成と「ゾス」式は、突き詰めると真逆の方法論ではない、ということ。これからも組織の在り方や育成について、皆さまと一緒に考えていきたいと思います。

