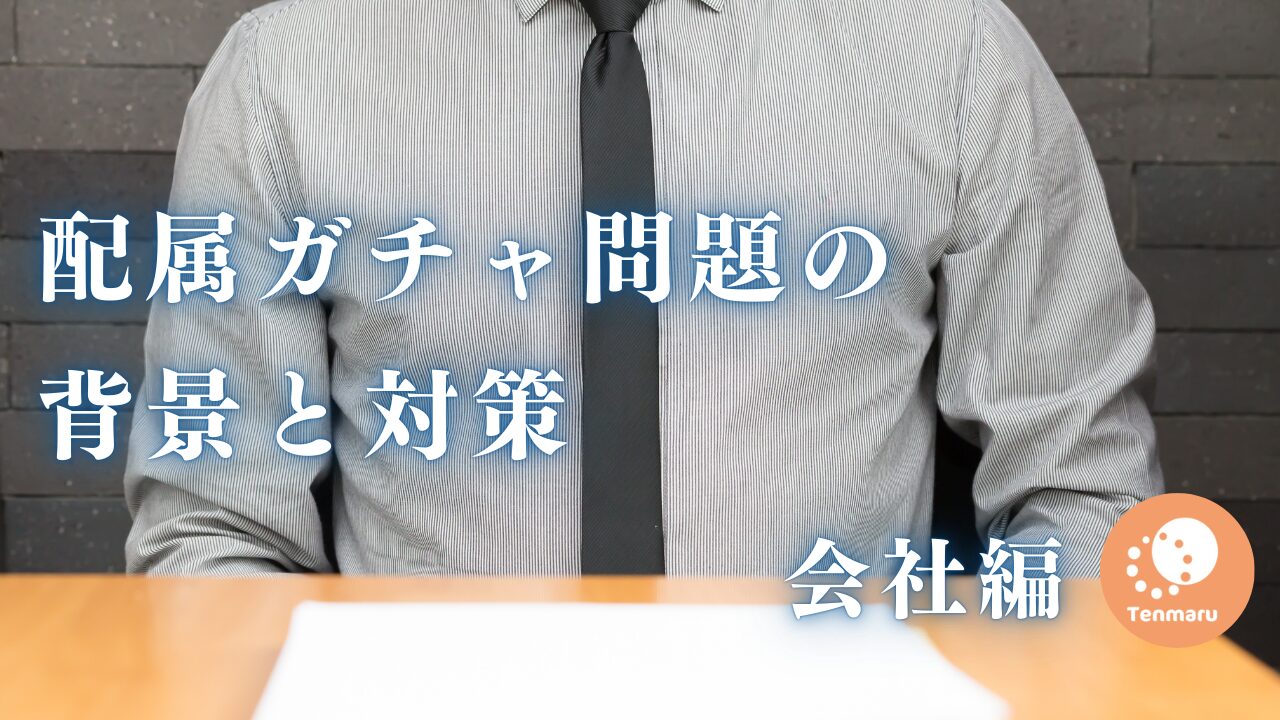皆さま、お盆はどのように過ごされましたか?
連日の猛暑で外に出るたびに汗だく…せっかくお休みでもこの暑さだとどこにも出かけたくない…と思うのは私だけでしょうか。
とはいえ、この暑さを吹っ飛ばすくらい、熱く過ごしたい今日この頃です。
さて、今回は前後編の後編として「配属ガチャ」問題の背景と対策—会社編
をお送りさせていただきます。
すでに浸透したと言っても過言ではない、「配属ガチャ」。
前編は、就活生向けにこの言葉の本当の意味と、「ハズレ」の認識について、就活生や若手社員の皆さまには、納得して頂ける部分と少々耳の痛い内容をお話しさせていただきました。
- 前編を見逃した方はこちら▼

この「配属ガチャ」という言葉、会社の経営者や人事部の方にはどのように響くでしょう、恐らくあまりいい気持ちはしないのではないでしょう。
しかし、言葉として認知され、実際に就活生が使用しているという現実があります。会社としては当然、言われたくない、言われるのを避けたいと考えるかと思います。
では、どうすれば「配属ガチャ」と言われないようになるのか。
…の前に、そもそも「配属ガチャ」という言葉を、企業としてどうとらえればいいのか、まずはそこからお話させていただきたいと思います。
前編のおさらい
まずは前編でお話させていただいた内容を、ざっくりと抜粋させていただきます。
・「配属ガチャ」という言葉の生まれる背景として、希望部署や勤務地が運次第で決まるように感じている就活生が多くいるということ。多くの場合、ネガティブな意味で使われています。
・しかし、実際の配属はけっして“運”などではなく、企業の経営戦略や人員計画、成長のための配置など、必ず合理的な理由があるはずです。
・就活生が“ハズレ”と感じる例としては、希望と違う部署・勤務地、上司との相性など。
・希望通りにならない主な理由としては、経営戦略上の必要性、スキルや適性を見て成長を促すための配置など。また、まずは現場経験を積ませる意図も。
・ 新卒採用は即戦力としてではなく、組織文化や価値観を共有し、会社と共に成長する人材して採用しています。企業は新入社員を貴重な未来の戦力と考え、育成し、活躍できるよう大切にしていきたいと考えています。つまり、希望に添わない配属は必ずしもミスマッチとは限らないのです。
・配属を“ガチャのハズレ”と決めつける前に理由を考えてみましょう。入社前から企業理解・仕事理解を深め、ミスマッチを防ぐなどです。
・それでも納得できない場合はより成長し、評価してくれる環境を探すのも一つの選択です。「配属ガチャ」に振り回されず、配属を未来へのスタートラインとして捉えてください。
…と、このような内容となっておりました。いかがでしょうか。
会社側としてはその通り!とご納得いただけるのではないでしょうか。
売り手市場の弊害
上記のように、本質的に配属とは「ガチャ」でも「運」でもなく、必ず会社経営上の合理的な理由が存在します。
にも関わらず、会社側の視点に立つと、最近の傾向として少々この言葉に怯えているような、恐れているような印象を受けます。
少し検索しただけでも、「就活生に選ばれるには」「内定辞退防止のため」といった情報が多く上がります。(コラムで私も同じようなことを書いてもいるのですが…)
しかし、上記にもあるように、配属には、御社にとって「合理的理由」があるはずなのです。
にも関わらず、最近は企業側が「ガチャ」という言葉を受け入れてしまっているようにすら感じる時があるのです。
これはひとえに「売り手市場」の弊害なのかなと感じます。
今や新卒は貴重な、貴重な人材です。会社が「選ばれる」側になっています。それは事実です。
しかし「ガチャ」という言葉を真に受けて、就活生の顔色をうかがいながら腫れ物に触るような対応をする必要はない…と感じるのです。
採用は「お見合い」
私は今、「会社が選ばれる側」である、と書きましたが、それはなぜでしょう。
もちろん就活生は複数の内定を得たうえで、企業をてんびんにかけるようなことをしているのは周知の事実です。
しかし、本来は、
「弊社はこのような会社であり、このような人材を求めている」と求人するものですし、就活生は
「自分はこのような人材であり、このような会社に入りたい」と自ら応募するもの。

つまり、どちらかが一方的に品定めするものではないということ。
以前も書きましたが、採用とは「お見合い」のようなもの。
こちらも参考になさってください!

お互いの長所や条件を理解し、徐々に関係を深めていく…本当に「お見合い」と同じ、だと思いませんか?
最近の企業は、就活生に選ばれたいあまり、就活生からの評価を少々気にし過ぎなのではないかなと感じることがあります。
就活生との「お見合い」で、企業は「選ばれたい」と、自社の魅力をアピールします。こんな良い条件がありますよ…
恐らくその中に「配属」の話も含まれてくるでしょう。
やり甲斐があり、成長できる条件のよい仕事です…と。
もちろん働きやすい環境にしていく会社努力は必要だと思います。
ただ、良く思われようと最初に見栄を張ってしまうと、後々ロクなことにならない、という部分もお見合いと似ているなと感じます。
空前の売り手市場でもある現在、就活生に選ばれるため、自社の良いところはどんどんアピールすべきですが、それが行き過ぎてしまい、就活生に喜ばれなさそうな要素はあまり出さないようにする、ということが起こらないで欲しいなと思います。
良いところばかりをアピールし内定を出しても、入社後にモチベーション低下を招いて思うように育成が出来なかったり、早期離職されることになり、会社にも就活生にも不幸な結末を迎えるだけだからです。
会社は「選ばれるもの」なのか問題
空前の売り手市場、恐らく就活生は、自分が企業を「選ぶ」側だと考えている方が多いかと思います。
しかし、上記のように、採用したい人材と、入社したい会社がマッチして内定を受ける、のが本来の就活です。
要は就活生も会社も、ともに「相手に選ばれる」必要があります。決して一方通行ではありません。
しかし、就活生の方が立場的に「選ぶ側」と本人達も、そして会社も感じるのはなぜでしょう。それはもちろん
「求人に対して就活生が少ない」からですね。
割合は確かにそうですが、しかしたったひとりの就活生を皆が取り合っているわけではありません。
御社に入社して欲しい人材はどんな人でしょう。当然ですが、新卒社員に具体的なスキルを期待する企業はほぼありません。
つまり「育てて戦力化したい人」を採用したいはずです。
すべての応募者に気に入られる必要はありません。
「会社として育てたい人材」が「必要人数」採用できればいいのです。
その「育って戦力となる人」はどんな人でしょう。
企業理念を理解共感し、仕事に必要なスキルを理解し、育成に応えてくれる人…ではないでしょうか。
そんな人であれば、どのような配属であっても
「それが会社の合理的な判断である」と理解してくれるはずです。
つまり、本来会社は「配属ガチャ」という言葉に必要以上に怯える必要はないのです。
ではどうすればいいのか
ここまでお読みいただければ自ずと「配属ガチャ」と言われてしまう理由も、その回避方法もわかるはずです。
「配属ガチャ」と言われてしまう理由、それは
「就活生と会社の相互理解不足」です。
就活生は自分を良く見せようと「ホンネ」を語らず、どのような配属でも頑張ります!などとアピールすることもあるでしょう。
そして会社は、就活生に「選んで」もらうため、表面上「良い会社」をアピールしてしまってはいないでしょうか。
また、選考の過程で入社後のイメージ、お互いの未来に対してしっかり納得できる対話はなされていますか。
選考過程や内定時の説明不足により、意に沿わない配属をされた(と勝手に感じた)新入社員が「配属ガチャ」という言葉を使う…。
つまり、「配属ガチャ」と言われないためには、内定者と企業の相互理解を深めていくしかないということです。
本当に効果的な対策
「配属ガチャ」と呼ばれること、そのものもあまりいい気がしない会社側ですが、具体的に「配属ガチャ」と言われて困ることは何でしょうか。
新入社員のモチベーションの低下、早期離職…たくさんありますね。
これらを防ぐにはどうすれば良いのか。
これは当然「配属」の前に対策しなければなりません。
つまりは選考過程や内定者の時から「配属ガチャ」と呼ばれるリスクは始まっているのです。
そこを補うこととして大切なのが、弊社でも提供している「内定者フォロー」ですね。
効果的な内定者フォローは、内定者に過剰に寄り添い、優しい言葉をかけるばかりでは意味がありません。
会社と内定者、お互いの価値観を共有し合い、理解を深める場、それが「内定者フォロー」です。
会社の配属方針や 新入社員のキャリア形成について、入社前に理解を深め、会社の理念を伝え、内定者のライフキャリアビジョンとすり合せ、 共に成長し同じ未来を描けるようになること。

これこそが、私の考える「配属ガチャ」と呼ばれなくなる、ただひとつの方法です。
会社の理念に共鳴してくれる新入社員は、配属の理由も納得し、自身のライフキャリアと会社の未来を重ね、より大きく成長する場と感じてくれるはずです。
企業は、新入社員の育成に一定の責任を持つべきと私は考えております。
新入社員とともに組織も成長します。
同じ方向を向き、一緒に進みましょう。
このように伝える場こそが「内定者フォロー」であり、「配属ガチャ」と呼ばれない方法なのではないでしょうか。
「配属ガチャ」という言葉は一見、就活生にも会社にも厳しいように響きますが、これを愚痴をこぼす「言い訳」のように使うことだけは避けたい。
「ハズレの配属」ではなく「相互理解不足」があっただけー
これを回避するには、やはり企業側からの働きかけも不可欠と感じます。
本当の意味で有用な「内定者フォロー」をぜひ、考えてみませんか。
内定者フォローアップ研修のお知らせ
26年卒「内定者フォローアップ」の研修プログラムをご用意しております。

入社後のビジョンを「会社が提示した道」ではなく、「自らの選択として納得し、望んだ道」としてとらえることができたとき、内定者のエンゲージメントは飛躍的に高まり、モチベーションを持続させながら入社への準備を進めることが可能になります。詳細は、お問合せ下さい!