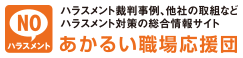すっかり涼しくなりました。ついこの前までエアコンを入れていたと思ったのですが…年々、秋らしい秋が短くなっているような気がします。
さて、皆様の会社におかれましても、「ハラスメント問題」、あれこれ対策されているかと思います。
コラムでも何度か「ハラスメント」に関してお話させていただいております。




今ではすっかり「当たり前」となった「ハラスメント対策」ですが、企業の対策が大きく進んだのが
パワーハラスメント関係及びセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント関係の法律改正です。中小企業に関しても2022年(令和4年)4月1日から義務化されております。
そうです、努力目標ではなく「義務」なのです。
現在では多くの企業様が「ハラスメント問題」を自分事としてとらえ、研修や窓口設置などの対策を行っております。
法律があろうとなかろうとハラスメントは決して許されるものではありません。しかし、義務化にともない、対策がより進んだことは非常に良いことだとも思います。
そして、このいわゆる「パワハラ法」、今年度にも改正がおこなわれたことはご存知でしょうか?
「就活ハラスメント法」対策義務化へ
「就活ハラスメント」、とても嫌な言葉ですね。
これまで就活ハラスメントの防止措置は、企業の義務ではなく、「実施するのが望ましい」というレベルにとどまっていましたが、2025年6月11日公布の改正男女雇用機会均等法により、就活セクハラの防止措置については実施が義務となりました。
そして、公布日から1年6カ月以内に施行予定。つまりは、こちらも間もなく「義務」となるわけです。
就活ハラスメント法案、正確には「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」ですが、では、一体何を持って「就活ハラスメント」となり得るのでしょうか。
ハラスメントとは、何か。
「ハラスメント」という言葉、いまや誰もが知っている言葉ですが、あらためて意味を確認していきましょう。
ハラスメントとは、
「相手が不快に感じる言動によって、相手の尊厳や安心を損なう行為」のこと。
たとえ悪意がなかったとしても、相手が「不快」「怖い」と感じれば、それはハラスメントにあたります。
悪意の有無ではなく、相手の感じ方によって定義されるハラスメント。
これは、たとえ発言が「善意」からであっても起こり得る、というお話はこちらでお伝えしております。

例えば、「女性には大変な仕事だろう」と気づかうつもりで仕事量を減らす、などは立派なハラスメントですが、こういった行いは「善意」からのもの。
職場での言葉づかい、態度、雑談のひとこと、そんなつもりはなくても、たとえ些細なことでも、相手が「ハラスメントだ」と感じれば、それはハラスメントです。このあたり、古い価値観から逃れられない方にとってあまりに主観的で、納得できないと感じるかもしれません。
では、就活の場面で起こる「ハラスメント」にはどのような問題があるのでしょうか。
「就活ハラスメント」とは?
「就活ハラスメント(就職活動中のハラスメント)」は、採用活動やインターンシップなどで、企業側が学生に対して不適切な言動を行い、学生が不快・不利益を感じるようなケースを指します。
たとえば以下のようなものが「ハラスメントにあたります。
・「彼氏いるの?」「可愛いね」などの容姿・恋愛への言及
・女性限定で結婚、出産、家庭観といったプライベートな質問をする
・食事や飲み会への誘い
・SNSでの私的な接触
・「内定を出すから」などの優位な立場を利用した発言
こうした行為は「明確な悪意」がなくても、内定の決定権を持つ者の言動は学生にとって強い圧力になるのは言うまでもありません。
断りづらい、逆らえない、その構造そのものがハラスメントを起こす、ということですね。
これら「ハラスメント」に関しては、こちらの内容が非常によくまとまっておりますので、ぜひ参考になさってください。
就活ハラスメントの実体
それでは、実際に就活現場では何が起きているのかを見てみましょう。
就活でのハラスメントとして圧倒的に多いとされているのがセクハラ、セクシャルハラスメントです。
「厚生労働省 令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査」からです。
「インターンシップ中にセクハラを経験した人」30.1%
「インターンシップ以外の就職活動中にセクハラを経験した人」31.9%
いずれも3割を超えているのです。
就活中にセクハラを受けた相手
「インターンシップを担当した自社従業員」(40%)
「採用面接担当者」
「企業説明会の担当者」
「OB・OG訪問を通じて知り合った従業員」(20%)
セクハラをしているのは当然、就活生にとってNoを言いにくい相手となっております。
このような状況のなか、企業はどのような対策をしているかというと、なんと半数近い企業が「何も実施していない」と回答しているのです。

このようなお話をすると中小規模企業の経営者様の中には
「大手と違ってハラスメント対策にリソースを回せない」というようなことをおっしゃる方がおられます。
しかし、対策の有無は企業規模で大きく違わない、という結果も出ております。
以上からこのようなことが言えるでしょうか。
「就活ハラスメント、特にセクハラが蔓延していると言っていい状況にも関わらず、企業の対策は進んでおらず、対策の有無は企業規模ではなく、コンプライアンス意識によるところが大きい」…
いかがでしょうか。この割合も、対策が進んでいないことも、非常に怖いことだなと感じます。
法の成立が意味するもの
では、就活ハラスメントを防止するにはどのような対策をしなければならないのでしょうか。
厚生労働省がまとめた「就活ハラスメント防止指針」では、企業には以下のような取り組みが求められています。
・採用・面接時のガイドライン整備
・社員・面接官への教育・研修
・学生からの相談・通報窓口の設置
・事案発生時の迅速かつ適切な対応
つまり、「就活ハラスメント」とは、「個人のモラルの問題」ではなく、組織として発生防止の仕組を整えるべき、ということです。
今回の法改正は、カスハラ、カスタマーハラスメントなども対象に含まれております。
今までは社員、つまり雇用する者に対して対策するのが「ハラスメント対策」だったものが、就活生を含む、企業と関わる者に拡大されたということ。
自社だけの問題であったハラスメント問題が、外部に対しても適用されることは、実は大きなリスクでもあります。
企業にとってのリスク
今やSNSを中心とした「炎上」は、毎日のように起こり、ブランドイメージを失墜させる企業は後をたちません。
就活ハラスメントが発生すると、被害を受けた学生本人だけでなく、企業そのものが大きな影響を受けます。
就活生は、内定が出るまで、いや入社するまでは「外部」の人間。情報を拡散することでのデメリットはせいぜい内定取り消しぐらいでしょうか。職を失うリスクを負った社員とは、情報拡散のハードルが低いと言えるでしょう。
「この会社の面接でこんなハラスメントを受けた!」
このような情報はSNSや口コミサイトで拡散、採用ブランドを大きく毀損するばかりか、せっかくの他内定者も辞退、採用コストが無駄になり、既存社員の意識低下、離職リスク増大、法令違反による行政指導や訴訟リスク…
非常に端的な言い方をすると、会社にとって「大きな損失」となる、ということです。
「ハラスメントを起こさない組織」をつくるには
こちらのコラム


などでもお伝えしていることになりますが、
ハラスメント問題が起こってしまう要因として、
「アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)」
「コミュニケーション問題」
などが挙げられます。
相談窓口を設置する、研修を実施するなど、各企業様におかれましてもそれぞれ対策しているかと思いますが、今後は「就活ハラスメント」という、言わば社外の人に対してもハラスメントを起こさなよう、より深く根本的に「ハラスメント問題」に取り組まなくてはならないのかもしれません。
つまり、「こういうことは止めましょう」「これを言ってはいけません」という、言動を表面的に整えるような通達では不十分、ということ。
例えば研修で異性の社員に性的なジョークを言うのは今の時代ではダメ!これを理解できたとして、女性の就活生に「結婚後は仕事を続けるつもりですか?」という質問がハラスメントに当たる、と気がつけない人は割といるのではないでしょうか。

違う立場の人のことを考える、相互理解、コミュニケーションの質を高めるなど、
「自分の言動がハラスメントかどうか判断できる人」に皆が成長できるよう、企業も対策していく必要があるのですね。
Tenmaruが提唱するハラスメント対策
弊社㈱Tenmaruが提案するハラスメント対策は以下の通りです。
・実践的かつ具体的な研修
実際にどのような状況が、言動がハラスメントなのか、なぜハラスメントなのかを具体的に学んでいきます。
・外部相談窓口の設置
外部窓口だからこそ公平性が保たれ、相談者の心理的ハードルを下げることによって相談しやすい窓口として機能します。
・社内相談窓口設置のお手伝い
・社内の相談窓口担当者へのトレーニング
ハラスメントに関する知識をインプット。ハラスメント窓口が機能するようお手伝いいたします。
・上司向けハラスメント研修
・経営ボードのハラスメント意識向上研修
上司から部下へのハラスメントが圧倒的に多いのが現状です。意識は上から変えていきましょう。
…その他、ピンポイントでのご相談も承ります。
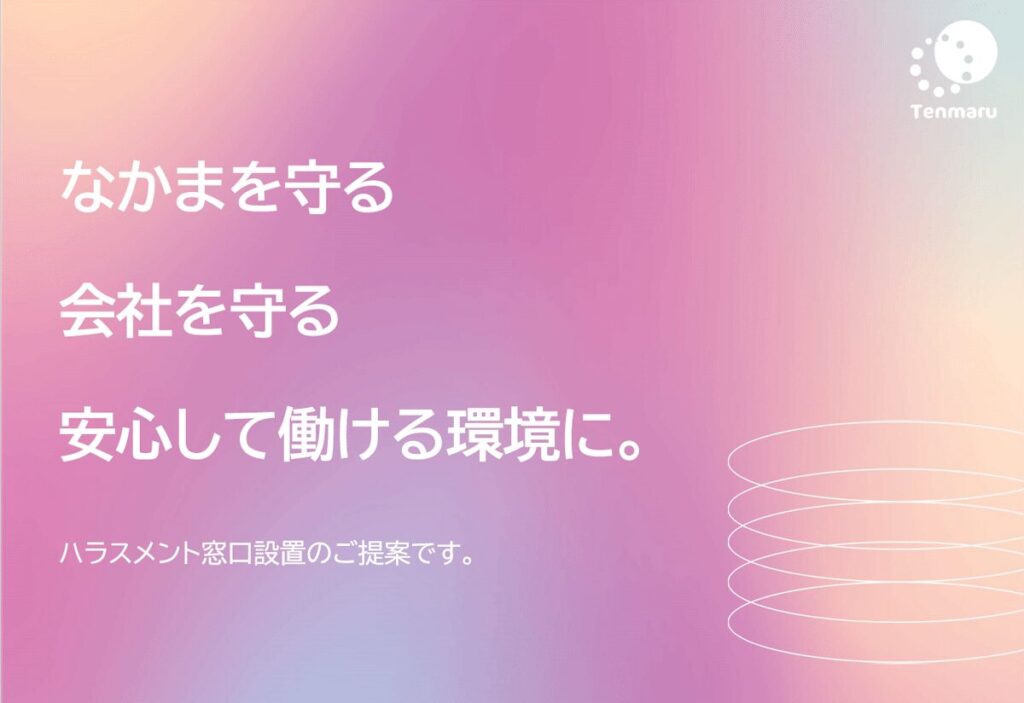
■サポート内容はこちらからダウンロードいただけます。
ハラスメント対策はルールを守るだけではなく、相互理解を育むことが欠かせません。Tenmaruではこれまで、ハラスメントの起こる構造そのものを理解し、再発を防ぐための「安全・尊重・信頼」を育てる仕組みをテーマに、研修や組織づくりを支援してきました。
「禁止する」ではなく、「気づける人を育てる」。これが㈱Tenmaruの考えるハラスメント対策です。そして、法律が整備されてきた今こそ、あらためて問われるのは“どんな組織をつくりたいか”。罰則を恐れるよりも、社員一人ひとりが安心して働ける環境をどう育てていくか。
Tenmaruは、制度と人の両輪で「ハラスメントが起きない組織づくり」に伴走します。安心があるから、挑戦できる。そんな風土を、これからも一緒に広げていきたいと願っております。